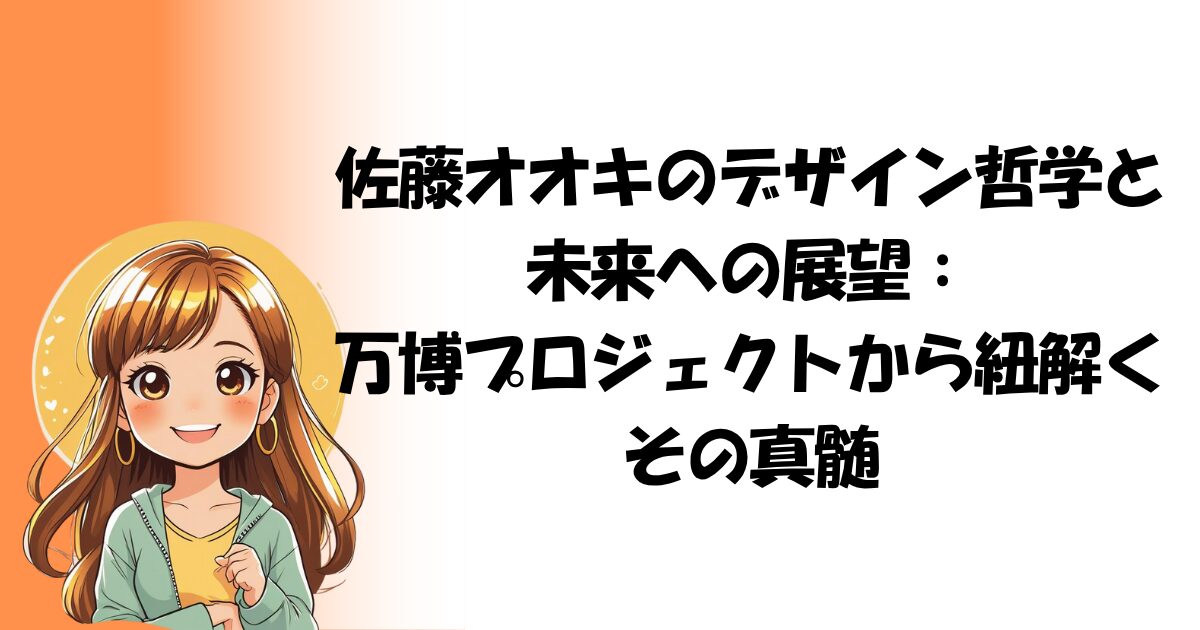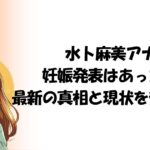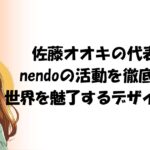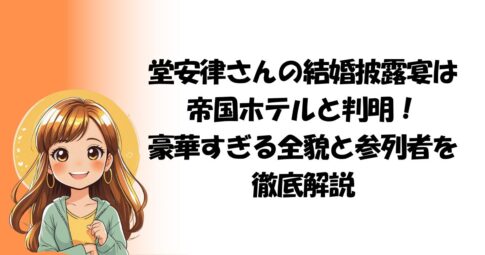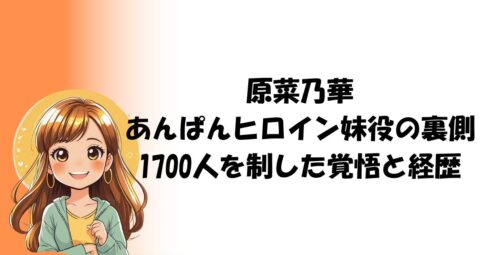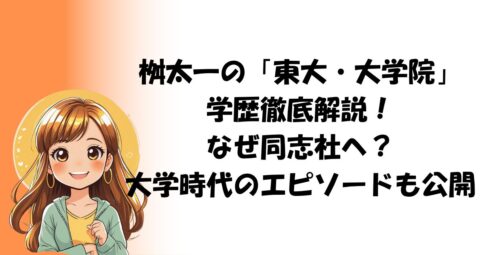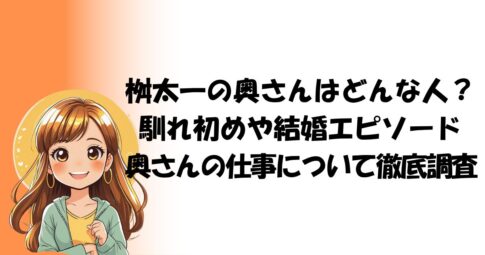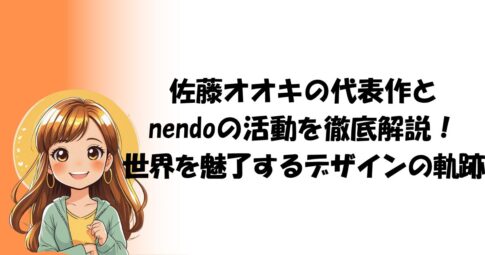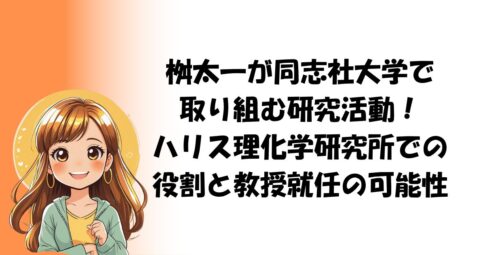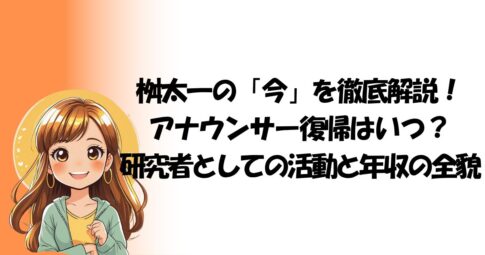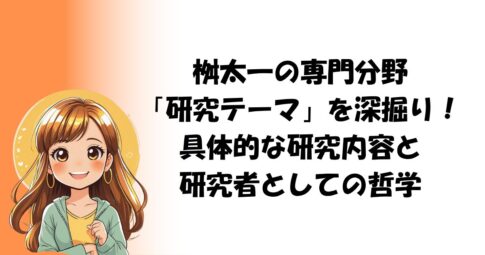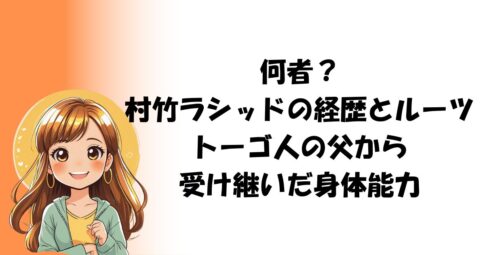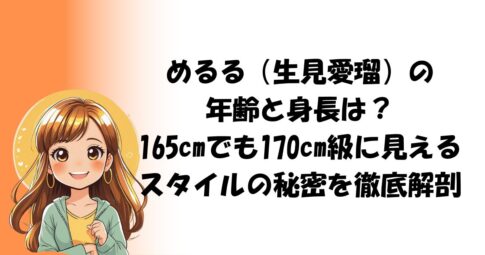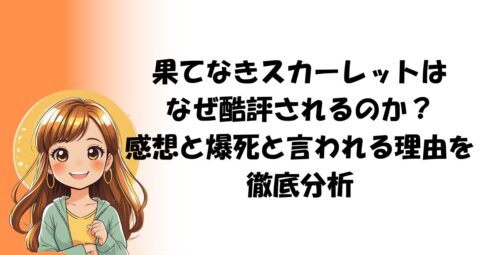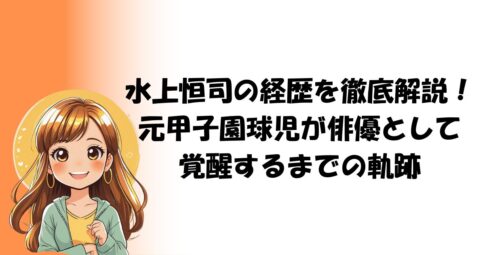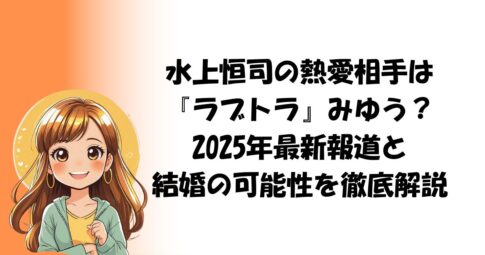世界的に活躍するデザイナー、佐藤オオキさんは、その革新的な作品だけでなく、独自の「いいデザイン」の哲学と、未来を見据えた活動でも注目を集めています。彼のデザインは、単に物の形を美しくするだけでなく、人々の思考や行動、さらには社会全体のあり方にまで影響を与える可能性を秘めています。
佐藤オオキさんは、プロダクトデザインの枠を超え、社会課題の解決や、デザインの可能性を広げることに貢献しています。彼の言葉からは、デザインの本質と、それを生み出す思考プロセスが垣間見えます。
この記事では、佐藤オオキさんが語る「いいデザイン」の真髄、日本のものづくりにおける「隠すこと」の価値、そして彼の発想術に迫ります。さらに、大阪・関西万博の日本館プロデュースに見る彼の社会貢献への姿勢や、常に挑戦し続けるnendoの未来像まで、その哲学と展望を徹底的に解説します。
目次
佐藤オオキが語る「いいデザイン」とは?その哲学と発想術に迫る
佐藤オオキさんは、数々の革新的なデザインを生み出す中で、独自の「いいデザイン」の哲学と発想術を確立しています。彼の言葉からは、デザインの本質と、それを生み出す思考プロセスが垣間見えます。
「オカンに電話で伝わる」デザイン思考の真意
佐藤オオキさんが語る「いいデザイン」の基準は、「オカンに電話で伝わるもの」という驚くほどシンプルな言葉に集約されています。これは、専門知識のない母親に電話で商品のコンセプトを伝えて「面白い」と感じてもらえるほど、直感的に伝達できるシンプルさと明快さを持つデザインを目指すという彼の哲学を示しています。この基準は、デザインが一部の専門家だけでなく、あらゆる人々に理解され、共感を呼ぶべきだという彼の強い信念に基づいています。

彼は、発想力は生まれつきのセンスではなく、努力によって身につけることができると繰り返し語っています。担当するすべてのプロジェクトに全力で向き合い、深く考え抜くことで解決策となるデザインを導き出しているといいます。この「オカンに電話で伝わる」という言葉は、ユーザー目線に立ち、いかに複雑な情報を分かりやすく伝えるかという、彼のデザイン思考の真髄を表していると言えるでしょう。
この考え方は、彼が初めて描いた絵本『コップってなんだっけ?』にも通じており、まるで世界的デザイナーの頭の中を覗き見しているかのような、シンプルで分かりやすいストーリーが展開されています。この絵本は、子供から大人まで、誰もがデザインのプロセスを楽しみながら、発想力を鍛えるきっかけとなることを意図して作られました。
日本のものづくりに見る「隠すこと」の価値とは?
佐藤オオキさんは、日本の伝統的なものづくりから現代のデザインへと継承された価値観として、海外のクリエイションとは対照的な「隠すこと」の価値を指摘しています。これは、単に情報を秘匿するのではなく、見る者に想像力や発見の喜びを与えるという、奥深い美意識に基づいています。
例えば、江戸時代の芸術家・本阿弥光悦の茶碗「熟柿(じゅくし)」の高台は、器をひっくり返さないと見えない部分にまで精緻な造形へのこだわりが見られます。これは、通常は見えない場所にこそ美しさや意味を込めるという、日本のものづくりに根ざした「隠すこと」の美学の象徴です。また、江戸時代の絵師・尾形乾山の茶碗では、春夏秋冬が描かれていても、季節に合わせてその面を客人に向けて差し出し、他の季節は「隠す」ようにデザインされています。これにより、一つの器の中に凝縮された四季の移ろいを、一度に全て見せるのではなく、その時々の季節に合わせて「見せる部分」を選ぶことで、より深い趣と物語性を生み出しています。
佐藤オオキさんは、現代の技術と「隠すこと」の手法を組み合わせた成功例として「ポケモンGO」を挙げます。リアルな空間にモンスターが隠れていて、スマホを使って「あぶり出す」ことで、単なるゲームを超えた発見の喜びとイベント性が生まれ、面白さが生まれると分析しています。これは、最初からすべてが見えていたら面白さが半減するという「隠すこと」の価値を、デジタル時代において見事に具現化した例と言えるでしょう。
彼は、海外のデザインがコミュニケーションを重視し、アイデアを分かりやすく伝えるのが前提であるのに対し、日本では「一を言って十を知るのが美徳」とされてきたと語ります。この「隠す」「隠さない」のさじ加減はプロジェクトによって大きく異なり、特に日本企業が海外市場を目指す際には、デザインの分かりにくさが原因でつまずく事例も少なくないと指摘しています。ユーザーの目線からタッチポイントを丁寧に見つめ、どの情報を「見せる」べきか、どの情報を「隠して」発見の余地を残すべきかを戦略的に考えることが、国際的なデザインにおいては極めて重要だと強調しています。
発想力は努力で身につけられる?佐藤オオキ流の思考法
佐藤オオキさんは、発想力は生まれつきのセンスではなく、努力によって身につけることができると明言しています。彼自身、常時400を超えるプロジェクトを同時進行させながらも、それぞれの案件に全力で向き合い、「考えて、考えて、考え抜いて」解決策となるデザインを導き出しているといいます。この「考え抜く」プロセスこそが、彼独自の思考法であり、発想力を鍛える鍵だと語ります。
彼の思考法は、日常生活に潜む不満や課題を見つけ、それを解決するための方法を考える「デザイン思考」に根ざしています。これは、デザイナーだけでなく、あらゆる分野で問題解決に取り組む上で役立つ本質的なスキルです。また、彼は常にニュートラルでいること、思考を固定化しないことを重視しており、「こうなりたい」や「こうすべき」といった固定観念にとらわれず、常にグレーゾーンという感覚でいることが、思わぬ可能性を開くポイントだと語ります。この柔軟な思考は、多様なクライアントの複雑な課題に対し、既成概念にとらわれない新しい解決策を見出す上で不可欠な要素となっています。
さらに、早稲田大学の学生たちへのメッセージとして、「楽な道と大変な道、二つあったら、ぜひ後者を選んでください。効率性や確実性を求めれば、可能性を狭めることになります。成功する保証なんてなくても、突き進む。それが自分の納得できる生き方につながるのだと思います」と述べています。これは、彼自身の「崖っぷちの手探り状態」から常に全力で挑戦し続ける仕事スタイルを反映しており、情熱を注げる仕事を見つけること、そして困難な道を選ぶことで得られる成長と達成感の重要性を伝えています。
佐藤オオキの今後の活動とデザイン界への展望
佐藤オオキさんとnendoは、現在も多岐にわたるプロジェクトに挑戦し続け、デザインの可能性を広げながら、社会課題の解決にも貢献しています。
常に挑戦を続けるnendoの未来像
nendoは、常時約400もの案件を同時進行させており、その半分以上が海外からの依頼だと言われています。彼らが多くのクライアントから評価される理由は、単に最終的なアウトプットを出すだけでなく、そこに至るまでのプロセスを大切にする姿勢にあります。クライアントがどんな壁にぶつかっているのか、課題抽出から深く関わり、常にクライアントに寄り添って柔軟な発想でアイデアを考えることを重視しています。
デザインに対するニーズが多様化する現代において、nendoは強い個性やテイストに固執するのではなく、クライアントが抱える課題を抽出し、常に寄り添って柔軟な発想でアイデアを考えることを重視しています。そのため、案件ごとに独自のデザインが生まれ、「nendoには代表作がない」と佐藤オオキさん自身が語るほど、そのアプローチは多岐にわたります。これは、プロダクトだけでなく、経営や事業といった会社の根幹部分にもデザインを取り入れ、組織の課題解決や技術力向上を支援するなど、デザインの領域を広げながら社会課題の解決に貢献しようとするnendoの未来像を示しています。
大阪・関西万博「日本館」総合プロデュース:循環と共生の未来を描く
現在(2025年)に開催されている大阪・関西万博において、佐藤オオキさんは「日本館」の総合プロデューサーを務めています。この日本館は、日建設計が建築デザインを手掛け、「いのちと、いのちの、あいだに」をテーマに掲げた円環状のパビリオンです。
この投稿をInstagramで見る
日本館の大きな特徴は、その持続可能性への深い配慮です。280組560枚もの国産スギを用いたCLT(クロスラミネートティンバー / 直交集成板)が使用され、「いのちのリレー」や「いのちの循環」を象徴的に表現しています。さらに、万博会場で発生する生ごみを回収し、微生物の働きで発酵分解することで発生するバイオガスを利用して、パビリオン敷地内で発電するバイオガスプラントを併設。「ごみを食べるパビリオン」として、資源の「循環」の価値を具現化しています。
佐藤オオキさんは、従来の博覧会パビリオンが展示内容と無関係な「ホワイトキューブ」として作られることが多かったのに対し、今回は展示計画と建築設計を一体的に進めることで、「展示と建築の融合」に挑んでいます。Plant Area、Farm Area、Factory Areaの3エリアで構成され、決まった順路はなく、どこから入っても「いのちの循環」について深く知ることができます。訪れる人々が五感で体験できるような、明るく開放的な吹き抜け空間や、トップライトからCLTを照らす柔らかい光の空間、展示に集中できる低い天井高の空間など、変化に富んだ「展示環境」を創出することを目指しています。
また、CLTの板と板の間には視線の通る隙間を設け、「外部と内部」「展示と建築」が連続して繋がり、循環とは異なるもう一つの「あいだ」を想起させる工夫も凝らされています。使用されるCLTの一部は、会期後に解体・返却され、新たな建築物としてリユースされる計画であり、仮設建築物としての時限性を踏まえながらも、最大限の持続可能性を追求しています。
この日本館は、佐藤オオキさんのデザイン哲学である「小さな“!”」を感じさせる工夫が随所に凝らされ、日本の美意識と自然感を体現しながら、未来の社会における「循環」と「共生」のあり方を示す、象徴的なプロジェクトと言えるでしょう。
佐藤オオキさんは、日本の社会が均質性から多様性へと変化している現在を、デザインが過去の蓄積を前向きに応用するための好機だと捉えています。彼が語る「立体感のあるマニュアル」の構築は、例えばサバの缶詰のパッケージのように、国によって好まれる表現が異なる場合に、シンプルなイラストで普遍的な理解を促すといった、柔軟な対応を可能にする考え方です。これは、海外と日本のデザインのギャップを超えるためにも役立つ、社会課題解決に向けたデザインの可能性を強く示唆していると言えるでしょう。
まとめ
佐藤オオキさんとnendoは、その革新的なデザイン哲学と、常に未来を見据えた活動で、世界のデザイン界を牽引し続けています。彼が提唱する「オカンに電話で伝わる」デザイン思考は、複雑な情報を直感的に伝えるシンプルさを追求し、日本の「隠すこと」の美学を現代に再解釈しています。
発想力は努力で身につけられるという信念のもと、多岐にわたるプロジェクトに挑戦し続けるnendoは、プロダクトデザインに留まらず、社会課題の解決にも貢献しています。大阪・関西万博の日本館総合プロデュースや、サステナブルな素材を活用したプロダクト開発、多様なユーザーに対応するデザインなど、その活動は未来のデザインの可能性を示唆しています。
佐藤オオキさんとnendoは、これからも私たちの生活や社会に新たな「!」をもたらし、デザインの力でより良い未来を創造していくことでしょう。